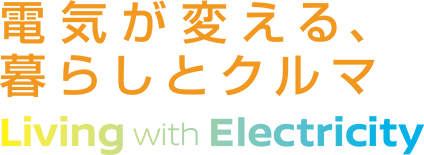![]()


日産ノートに初搭載された新しいパワートレインのe-POWERは、エンジンで発電してモーターだけで走る、新しい種類のEV(電気自動車)。エンジン車と同じように充電を気にせずに走ることができると同時に、エンジン車とはまるで異なる新しい運転感覚を味わうことができる。
「自分が思うように動いてくれることが、コンパクトカーだからこそ重要」と、新型ノートを担当した日本商品企画部の谷内陽子が語るように、思い描いた通りに加速する新鮮なフィーリングを感じる。ある程度まで回転が上がらないと力が出ないエンジンと違い、モーターは電流が流れた瞬間から力を発揮。したがって、アクセル操作に対する反応が素早いのだ。力強く、思いのままになる加速は、世界初の量産EVである日産リーフで培ったモーターの制御技術の賜物である。
e-POWERのもうひとつの特長は静かなこと。「乗っているみんなの会話が弾むようなクルマにしたい」と、谷内がこだわった部分だ。発電用エンジンは停止していることが多く、発電の際はロードノイズなどに紛れる車速域で作動するので騒音が気にならない。
運転が楽しいうえに、静かで快適。e-POWERは新次元の電気の走りで、クルマの常識を変えていくのだ。

e-POWERをひとことで表すと「自ら発電するEV」。日産リーフの優れたEVの仕組みと、専用エンジンで発電するシステムを組み合わせたものだ。発電専用のエンジンは、発電モーターを動かして電力を生む。エンジンは走行には関与しないので、最も発電効率がいい回転域だけで稼働。開発に携わった餌取秀一は「エンジンは市街地などでは停めて静かに走り、タイヤノイズが大きくなる車速が高いときにかけて、エンジン音がわかないようにしました」と、静かさにもこだわった。
発生した電力は駆動用バッテリーに蓄えられるが、いつでも発電できるe-POWERでは、バッテリーに大量の電力を蓄える必要がない。駆動用バッテリー担当の松葉暢男は、「シート下に収めるのに苦労しましたが、室内の広さを確保しました」と胸を張る。
バッテリーに蓄えた電力は駆動モーターを動かし、車両を加速させる。駆動モーターは日産リーフと同じもの。したがってe-POWERも、世界で最も売れているEVと同等のパフォーマンスを発揮する。
減速時は、駆動モーターが発電機として働き、電力を発生。そのエネルギーを電力に変換するこの仕組みを、回生ブレーキと呼ぶ。e-POWERでは、わずかな減速でも回生ブレーキが働くように設定している。
e-POWERという仕組みの面白いところは、エンジンが発電に専念して、
車両を走らせることには一切関与しないという点にある。また、モーターで走るという特性を利用して、
e-POWERでしか体験できない操縦感覚を提供するモードも用意。運転の常識が一変する。
発電専用エンジンには、日産の高効率な1.2Lエンジンをe-POWER用に改良したものを採用。
モーターは日産リーフと同じものを用いるので出力性能はほぼ同等、優れた走行性能を発揮する。
発電専用エンジンを備えるe-POWERはたくさんの電力を蓄える必要がないため、
駆動用のリチウムイオンバッテリーがコンパクト。

-
通常発進・走行時
駆動用バッテリー残量が充分なとき(エンジンOFF)
発電用エンジンは停止、バッテリーで走行。
発進直後から力強く加速、エンジン音が聞こえないので静か*1。
-
通常発進・走行時
駆動用バッテリー残量が少ないとき(エンジンON)
発電用エンジンを稼働、発電した電力を充電しながら走行。
エンジン回転が一定であることと防音対策によって、静かな走りを楽しめる。
-
急加速・登坂時
電力フル供給で走行(エンジンON)
発電機とバッテリーの両方から電力を供給。
モーターに大電力を供給することで出力をアップ、
一気に加速する力強い走りを実現。
-
減速・降坂時
駆動モーター走行(エンジンOFF)
回生発電した電力をバッテリーに充電。
減速時にはエンジンを停止*2し、回生発電した電力をしっかりと充電する。

- *1ヒーター使用時等には発電用エンジンが始動します。
- *2駆動用バッテリーの充電量が高い状態では、放電のためエンジンが回ります。また、エアコン使用時にはエンジンが回る場合があります。
モーターによるなめらかで力強い走りをさらにバリエーション豊かに楽しめるように、e-POWERには3つの走行モードを用意している。
『NORMALモード』は、エンジン車から乗り替えても違和感のない走行モード。それでも十分に気持ちいい加速を味わえる。
一方、『e-POWER Drive』を選ぶと、今までにはない斬新な走行感覚が体験できる。日本商品企画部の谷内は「e-POWERをとことん味わいたいなら『Sモード』で楽しんでほしい。『NORMALモード』に比べて加速も減速も強くなり、キビキビとした走りが楽しめます。また、アクセル操作だけで速度をコントロールできるので、加速と減速を繰り返す市街地や、カーブの手前でスピードを落とさなければいけない山道では、アクセルとブレーキの踏み替えが減るのでドライバーの負担も減ります」と語る。ひとつのペダルを操作するだけでクルマを操る、新しい運転の楽しさがあるというのだ。
『e-POWER Drive』には電力消費を抑える『ECOモード』も設定。「3つのモードを使い分け、エコを意識した優しい走行性能から、力強い加速、未体験の運転感覚まで、さまざまな表情を楽しんでいただきたい」というのが開発者の願いだ。
私たちの生活に電気は欠かせない存在。
安定した電力供給を確保するため、これまで存在しなかった発電技術が注目されている。
電力自由化がはじまった2016年は日本の電力事情における転換期となった。生活するためのツールの多くがデジタル化し、電気に対するニーズが高まる一方で、現状の供給方法だけではまかない切れなくなっている。そこで注目を集めているのが、太陽光、風力、水力といった自然エネルギーを活かした発電や新しい発電技術だ。もちろん、今すぐそれらにシフトすることは難しいが、少しずつ移行できればいいと、波力発電の研究を行っている東京大学 生産技術研究所の林昌奎教授は話す。
「自然エネルギーは天候などの影響を受けるため不安定です。状況によって余ったり、足りなくなったりする。これから進化する新しい発電方法を組み合わせ、互いを補っていくようになれば、生活に十分な電力を確保できるかもしれません」
私たちの暮らしには今後ますます電気が重要になる。従来の発電技術、自然エネルギー、そして新しい発電技術を組み合わせながら、効率よく電気を活用することが必要になる。そんな未来につながる新しい発電技術をいくつか紹介しよう。
先日、岩手県に国内初となる波力発電所が設置された。その開発、研究を主導した林昌奎教授は、10年後を目処に本格稼働を目指していると語る。波力発電が未だに日本で普及していない理由のひとつが、あらゆる場所に設置可能な規格ができていないこと。風力や太陽光は、高さに制限がない空に向かって設置される。それに対して海は、深さや幅など環境がばらばら。林教授はこの問題の対策となる発電所をつくったのだ。
「日本は島国なので、波のエネルギーがたくさんあります。しかし、大きな波が立つ沖合に大きな発電所を構えればよいかといったらそうではありません。規模が大きければ、コストがかかりますから電気代も上がってしまう。私が着目したのは水深がおよそ3~4mと浅い防波堤沿い。沖合に比べると高い波は起きないのですが、似た環境が400カ所近くあり、きちんとエネルギーを確保できて、かつ比較的安全です。そこに、太陽光パネルのように量産ができる、コンパクトな発電所をいくつも設置する。そうすれば、1カ所から得られる電力が少なかったとしても、総合的には大きなエネルギーがつくれると考えました」
現状は送電線を利用した仕組みをとっているが、今後、充電ステーションとしての機能をもちEVも加われば、電気をつくって運ぶという一連の流れを実現させられる可能性が生まれる。


波力発電所が設置された場所は、久慈湾玉の脇地区。海の中に波の力を受ける板があり、その上の発電装置につながるシンプルな構造になっている。
2008・09年にJR東京駅でユニークな実験が行われた。改札の間に、踏むと電気が生まれる床発電装置が敷かれたのだ。そのアイデアを考案したのは慶応義塾大学 環境情報学部教授の武藤佳恭教授。1日に通行する人の数は約7万、この装置によって自動改札に使われる電力(ゲートの開閉など)をまかなえることが立証された。画期的な発電方法だが、ほかにも意義があるという。
「東京駅での実験の後、上海万博で展示し人気を博しました。床発電は誰でも参加できる人力発電。自らが電源となるような感覚で発電を楽しむことで、電気に対して意識的になってもらえると思うのです」
床発電の面白さは人が動く場所ならどこでも応用できる点だ。したがって大規模なイベントやフィットネスクラブと組み合わされば、より効果的かもしれない。


JR東京駅での実験の光景。改札を通るだけで電気が生まれる画期的な仕組みだ。左の写真で顔を覗かせている金属のようなもの(ピエゾ素子)が発生源になっている。

ヴィッセル神戸 スタジアムにも床発電装置を設置。観客が興奮すると発電量が上がるそうだ。
バイオマス発電は日本でも実際に稼働している発電所がいくつかあるため、ご存じの方も多いだろう。しかし、まだ課題が残っていると語るのはグリーン・エネルギー研究所の永野正朗さんだ。
「バイオマス発電は枝葉や端尺材など、木材として使われない部分の林地残材を燃やして電力に変えています。それは木全体からすると数%なのですが、塵が積もって大量に余っている。林業を営んでいる人にとって不要な存在なわけですが、その有効性を知れば可能性が広がります。不要なものが電力に生まれ変わると実感してもらうことが重要なのです」
グリーン・エネルギー研究所では一般家庭の庭木など、個人が持ち込んだ枝葉も買い取っている。自らが資材を提供する立場になることで社会貢献もできる。さらに森林保全・育成への資金還流も行っているという。地域のなかで木を中心にした循環が生まれるのだ。


グリーン・エネルギー研究所の工場が位置するのは、日本で最も森林率が高い高知県。地元で出たものを原料にしているため安定した供給が可能な上、運送雇用も生まれているという。
※本記事は2016年12月1日時点の情報を元に作成されております。